勉強会 セカンドライフと生命保険「生命保険を上手に見直して、豊かなセカンドライフを送りましょう」
日時 2026年1月19日(月)13:30- 場所 広島市消費生活センター研修室
講師 生命保険協会広島県協会 事務局長 西原 和也 氏
主催 広島消費者協会 参加者40名
概要 経済力はどれほどなのか、健康上の不安はどの程度なのか、病気治療も含めどのようなセカンドライフを送りたいのかを整理し、死亡や医療のリスクに対する備えを公的補償も含めよく検討し、今の保険加入状況をつぶさに理解し、場合にによっては、掛け金を減額したり、特約を解除したり、転換したりするなど、見直すことを推奨されました。また、病気等で意思表示できないときに備え、指定代理請求制度や家族登録制度の紹介がありました。
広島県「減らそう犯罪」推進会議 会長コメント
今年3月に広島消費者協会の会長に就任しました西村と申します。皆様方には、平素から協会に対しましてご理解ご協力を賜り、この場をお借りしてお礼を申し上げます。
さて、新聞を開きますと連日のように詐欺の被害額や不審電話についての記事が載っています。記事を読んでいる分には、自分とは関係ないよそ事に感じますが、そうは言っていられない状況です。我が家の固定電話に「未納料金が発生しています。本日でこの回線は使えなくなります。詳しくお知りになりたい方は1を押してください。」という電話が4~5回かかってきました。また、当協会の職員の携帯電話には、京都府警と名乗る者から、〇〇さんですかと、電話がありました。直ぐに切ったとのことですが、先方は名前を知っており、気持ちが悪いと言っておりました。
こうした中、消費者協会では7月に啓発活動として「特殊詐欺・侵入犯防止セミナー」を企画しました。講師は携帯会社の方と県警の方です。会員だけでは定員まで集まらないと思い、広報誌「市民と市政」でも参加者を募ったところ、定員30名を超える想定を大幅に上回る応募者がありました。普段、私どもの開催する講演会、勉強会には、なかなか参加者が集まらない中、この問題への関心の高さを実感しました。こうしたセミナーを引き続き、継続的に開催したいと考えております。
また、犯罪とすぐには言えないまでも、消費者が被害を受ける事象も最近多発しています。SNSの広告を見てお試しや1回だけだと思ったら定期購入だった、広告とは異なる商品が届いた、遺品整理を依頼したら聞いていた金額より高額に請求された、置き配で届いた商品がなくなっていたなど。こうした問題についても、今日、お集まりのみなさま方と連携して、消費者が安心、安全かつ円滑に生活ができるよう、積極的に取り組んでいきたいと考えております。引き続き、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。
2025年12月19日 広島消費者協会 会長 西村千賀子
市民防災講座「自然災害に備える」への参加
日時 2025年12月1日(月)14:00- 場所 TKPガーデンシティ広島駅前ホール
主催 京都大学
内容 地質から隠れた土砂災害リスクを見抜く 京都大学 准教授 松澤 真 氏
広島でも起きる?線状降水帯豪雨と気候変動 京都大学 助教 仲 ゆかり 氏
災害から身を守るために 広島市災害対策課 課長補佐 泉 浩平 氏
JR西日本旅客鉄道株式会社 執行役員 佐伯 祥一 氏
参加者 会員1名
講演概要
ごみ減らそうデー店頭キャンペーン(12月)
日時:2025年12月1日(月)11:00~ 場所:ユアーズ白木店
・ごみ減量・食品ロス削減啓発のぼり、パネルの掲示、啓発チラシの配布、買い物袋持参率の調査、ごみ減量・食品ロス削減に関するアンケートの実施、エコグッズの提供などを行いました。
「SNS時代のICTリテラシー」向上セミナーへの参加
日時 2025年11月21日(金)13:30- 場所 TKPガーデンシティ広島駅前大橋
主催 総務省中国総合通信局
内容 ・偽・誤情報等の現状を踏まえた総務省の取組み(総務省情報活用支援室長 竹下勝 氏)
・SNS時代のメディアリテラシー(広島大学大学院准教授 匹田篤 氏)
参加者 会員1名
募集チラシ
消費者のつどい2025への参加
日時 2025年11月13日(木)13:00- 場所 サテライトキャンパスひろしま
主催 広島県、広島県消費者団体連絡協議会
内容 第一部 講演会 演台「ネット広告に関する消費者トラブルの最近動向と対処法」
第二部 消費者団体活動報告(広島県地域女性団体連絡協議会、呉市消費者協会)
参加者 会員5名
コカ・コーラ広島工場見学
日時:2025年11月6日(木) 場所:コカ・コーラ広島工場(三原市) 主催:広島消費者協会
まずシアター上映で旧本郷工場の被災から広島工場への復興の歩みを映像や写真で見ることができました。また、コカ・コーラ誕生(1886年)から130年以上にわたり世界中でコカ・コーラは味も変わらず保存料も合成香料も一切使っていないことを知りました。次に製造工程見学/体感ブーで「製造工程を見る」ことに加え体感ブースでは壁全体にスマートフォンのフラッシュに反応する特殊なシートがほどこされ肉眼では見えなかった図柄がフラッシュにより浮かんでは消えるという瞬間的な変化の様子を見ることで、視覚による「冷却・炭酸注入」の工程の体感ができました。最後に工場全体の窓にソーラー発電シートがあったことに驚きました。
参加者:24名
フレスタ サステナブルレポート 勉強会
日時:2025年11月10日(月)13:30- 場所:広島市消費生活センター研修室
講師:㈱フレスタフォールディングス 取締役 宗兼伴恵 氏
主催:広島消費者協会
演題:フレスタグループ地域と取り組むSDGs
フレスタ様の取り組まれている、CO2削減や食品ロス、プラスチック削減やリサイクルの取組み、産官学地域連携で地元を元気にするプロジェクトなどを学びました。「ココロ、カラダにスマイル。」を「アシタ、ミライに、スマイル。」へつなげて、フレスタ様はヘルシストスーパーとして持続可能な社会の実現を目指されています。
参加者:25名

産地視察交流会(江田島オリーブファクトリ、沖山工房)
日時:2025年10月30日(木)
場所:江田島オリーブファクトリ、江田島焼 沖山工房
参加者:27名(地区会員24名、一般会員3名)

法務省中国矯正管区新製品開発コンクール審査員
日時:2025年10月29日(水)13:00~ 場所:広島刑務所(広島市中区)
主催:法務省中国矯正管区
概要:中国地方の七つの刑務所の受刑者が作った26品の審査
ひろしまの乗合バス事業の未来を考える会
日時:2025年10月27日(月) 14:00- 場所:サテライトキャンパスひろしま502大講義室
登壇者:広島大学大学院 教授 藤原章正 氏(ファシリテーター)、広島市 路線バス・生活交通担当 課長 三浦潤也 氏、広島電鉄株式会社 交通政策課 課長 進矢光明 氏、広島バス株式会社 営業本部運輸部 次長 平岡祐介 氏、広島消費者協会 理事・顧問 栗原理乗合
概要:バス事業は人口減少やモータリゼーションの進展、コロナ禍を契機とした人々の行動変容による利用者減、運転手不足など厳しい経営環境にあります。一方、利用者からは新しい乗車券システムの導入による使いづらさや運賃も含めた改善点が指摘されています。事業者、行政、利用者が集い、市民にとって欠かせない重要な交通手段である乗合バスの未来について議論しました。
参加者:63名(会員17名、一般46名)
報道:RCC中国放送
食品ロス削減イベント「スマイル!ひろしま広場」参加
日時:2025年10月26日(日)11:00~ 場所:シャレオ中央広場
主催:広島市ごみ減量・リサイクル実行委員会
内容:食品ロス削減の啓発(スタンプラリー受付ほか) 参加者:会員4名
幌延深地層研究センター(高レベル放射性廃棄物地層処分研究施設)見学
日時:2025年10月22日(水) 参加者:7名
「NUMO 選択型学習支援事業」の御支援により、北海道幌延町にある幌延深地層研究センターの施設見学に参加いたしました。原子力発電所から出る使用済燃料から、燃料としてまだ使えるウランとプルトニウムを回収した後に残る高レベル放射性廃棄物を、最終的に地下深い地層中に処分することが計画されている中、同センターは、高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発を行うことにより、地層処分の技術的な信頼性を実際の深地層での試験研究等を通じて確認することを目的とされています。同センターでは、深さ約500mの立坑を3本実際に掘削し、深度の深い地層の実態や保存の安全性などを緻密詳細に研究されています。放射性廃棄物はガラス成分と一体化されたガラス固化体しオーバーパックと呼ばれる金属性の容器に閉じ込め、さらには粘土で作られた緩衝材で包みこまれ地下300m以深の地表の自然災害(地震等)や人的影響(戦争等)を受けにくく地下水の流れが遅く物質が動きにくい、酸素がほとんどなく金属が錆びにくいところへ閉じ込める計画です。また、製造直後のガラス固化体は表面温度200~300度で表面の放射線量は1,500Sv/hで約20秒弱で100%の割合で人は死に至り天然ウランと同様の放射能レベルになるまでには数万年が必要です。こうしたガラス固化体はすでに約2,500本が高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター(青森県六ヶ所村)などに保管されているが、最終処分先が未だ見つかっていない現状があります。このように非常に扱いの困る放射性廃棄物処分の安全性を高めるため、必要となる技術の高度化や信頼性向上のために国が資金と英知を結集されていることを実感いたしました。
参加者:7名


幌延深地層研究センター (写真提供:日本原子力研究開発機構)
高市新政権発足 会長 コメント
自公政権が続いたこの約30年間、景気が良いとの実感は乏しく、世界の平均年収順位も20位程度まで低迷する中で、公明党に代わって新たな政党が政権に加わることによる政治の大きな変革を期待いたします。食料品の消費税を一定期間0%とすることは歓迎いたします。一方で財政規律に配慮しながら取り組んでいただきたい。一時療法ではなく手取り収入の向上や物価安定などに結び付く自公政権ではできなかった抜本的な経済、景気対策の実行を新政権に期待します。2025年10月22日 広島消費者協会 会長 西村千賀子
牛乳・乳製品利用料理コンクール審査員
日時:2025年10月18日(土)13:00~ 場所:進徳女子高等学校(広島市南区)
主催:広島県牛乳普及協会
概要:113人の応募者から選ばれた12人が、乳製品で自ら制限時間60分で調理した料理を審査。上位2名は11月15日開催予定の中国大会へ選出
特殊詐欺・侵入犯防止セミナー
日時:2025年10月16日(木)14:00~16:00 場所:広島市消費生活センター研修室 主催:広島消費者協会
講師:ソフトバンク株式会社 上田昌宏 氏、広島県警察本部生活安全課巡査部長 中村浩司 氏
主催:広島消費者協会
概要:特殊詐欺の種類、実態の紹介、だまされない工夫などを実際に最新のスマートフォンや広島県警の開発されたイーラーニングも使いながら学びました。
参加者:20名
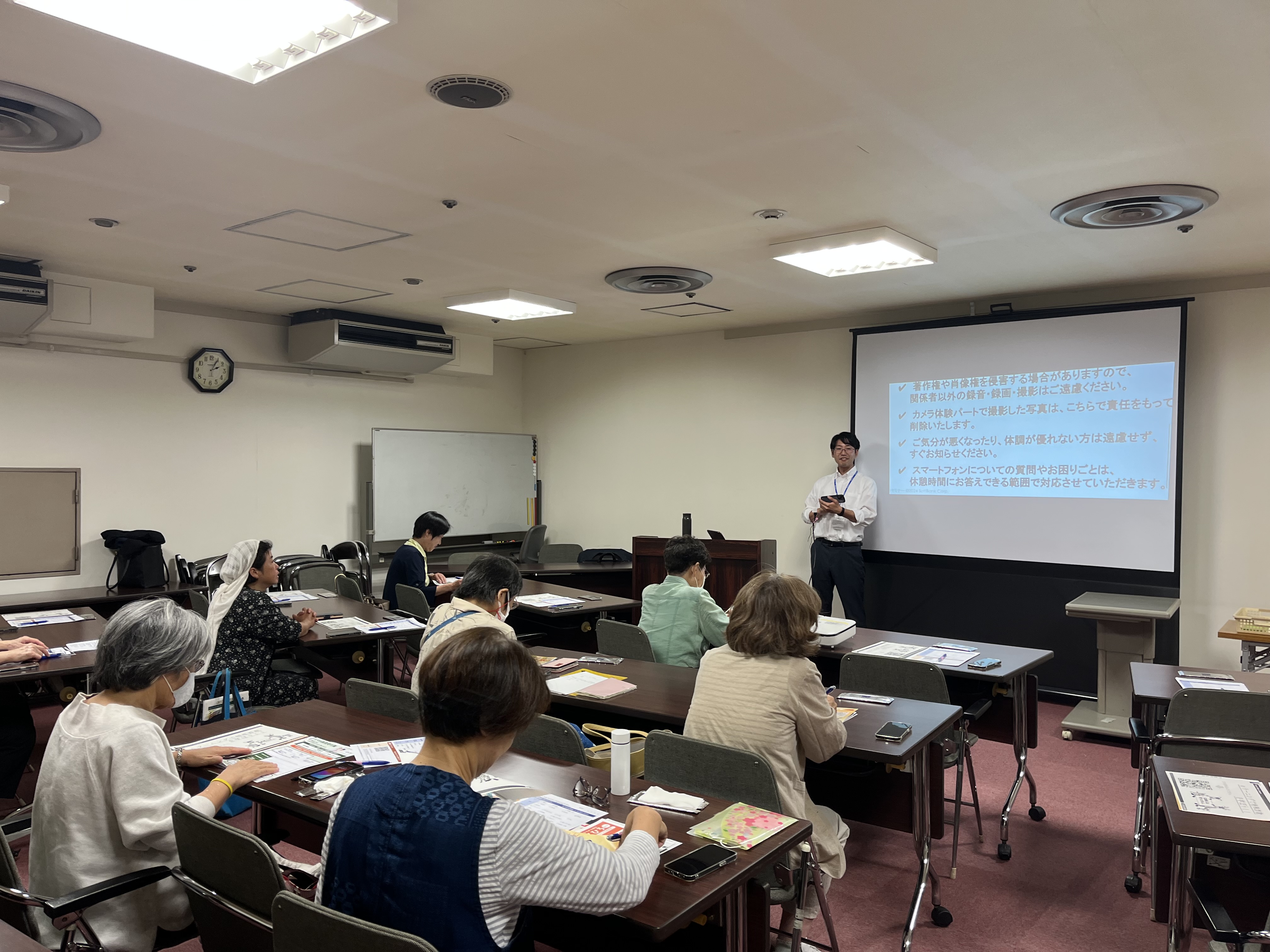
消費者大学(第8回:最終回)「インターネット~デジタルサービスの普及とリスク」
日時:2025年10月11日(土)13:30~15:30 場所:広島市消費生活センター研修室
講師:広島市電子メディア協議会 インストラクター 内海裕一朗 氏
参加者:16名

高レベル放射性廃棄物地層処分 勉強会
日時:2025年10月6日(月)13:00~15:15 場所:広島市消費生活センター研修室 参加者:8名
講師:原子力発電環境整備機構(NUMO) 地域交流部専門部長 多田直和 氏 課長代理 米山智巳 氏
概要:幌延深地層研究施設の視察前に、高レベル放射性廃棄物地層処分の講師をお招きし勉強会を開催しました。
高レベル放射性廃棄物の特性・量、具体的な保存方法、地下深部の特徴、多重バリアシステム、地処分場の概 要、処分地選定プロセス・現況などを学びました。高レベル放射性廃棄物地層処分のリスク管理が現行取り得 る最高水準にあることを理解しました。
消費者大学(第7回)「環境問題~消費者としてできること~」
日時:2025年10月4日(土)13:30~15:30 場所:広島市消費生活センター研修室
講師:広島大学大学院 教授 中坪 孝之 氏
参加者:18名

タクシー利用者懇談会
日時:2025年10月3日(金)13:30- 場所:広島県タクシー協会(広島市西区)
概要:タクシー事業の現状、運賃改定申請の概要、サービス向上の取組みについて
主催:広島タクシー協会 参加者:幹事1名
ごみ減らそうデー店頭キャンペーン(10月)
日時:2025年10月1日(水)11:00~ 場所:コープ西風新都
・ごみ減量・食品ロス削減啓発のぼり、パネルの掲示、啓発チラシの配布、買い物袋持参率の調査、ごみ減量・食品ロス削減に関するアンケートの実施、エコグッズの提供などを行いました。
消費者大学(第6回)「生活設計:これからの暮し整理~モノ・コト・住まい~」
日時:2025年9月27日(土)13:30~15:30 場所:広島市消費生活センター研修室
講師:(一社)さくらブリッジ 理事 湯上 みどり 氏
参加者:19名

消費者大学(第5回)「衣生活:エシカルな片付け~あふれるモノたちを手離す~」
日時:2025年9月20日(土)13:30~15:30 場所:広島市消費生活センター研修室
講師:ライフオーガナイザー 南方 佐知子 氏
参加者:12名

消費者大学(第4回)「食生活:心が整い身体が元気になる秘訣」
日時:2025年9月13日(土)13:30~15:30 場所:広島市消費生活センター研修室
講師:(一社)ローカリズム推進楽会 平山 友美 氏、菅野 美穂子 氏
参加者:28名

生命保険協会・消費者意見交換会
日時:2025年9月10日(水)13:30~ 場所:広島市消費生活センター研修室
・生命保険に係る最新動向、契約者とのトラブルなど、意見交換しました。
参加者:1名
会報「消費生活ひろしま」99号発行
直近の協会の活動を取りまとめた「消費生活ひろしま99号」を発行いたしました(令和7年9月)。
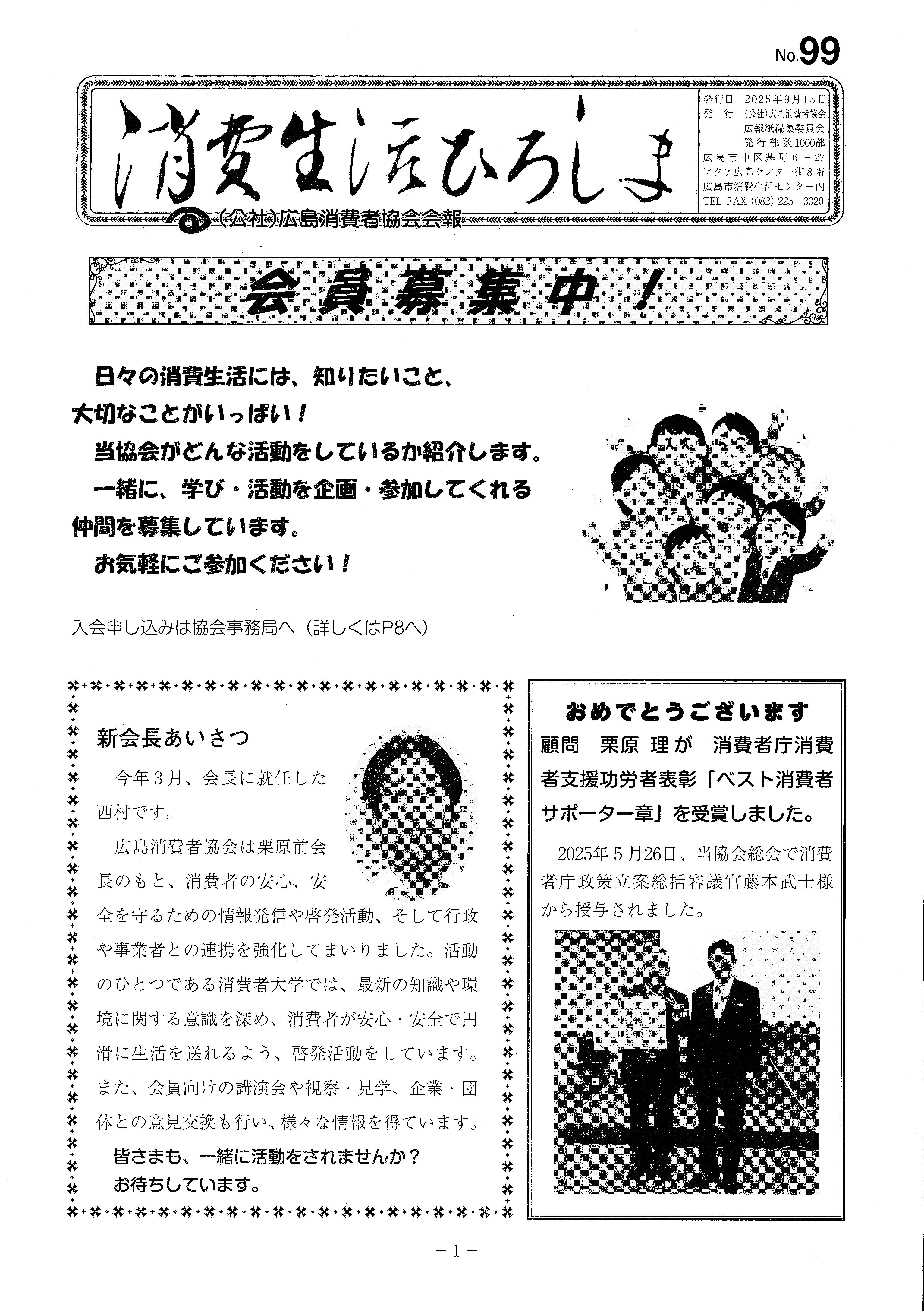
消費者大学(第3回)「くらしの安全:災害への備えについて」
日時:2025年9月6日(土)13:30~15:30 場所:広島市消費生活センター研修室
講師:広島市災害予防課 主事 坂本 達哉 氏 広島市河川予防課 技師 大西 晃洋 氏
参加者:26名

戸坂地区勉強会「家族信託を知ろう~家族信託の基本~」
日時:2025年9月4日(木)13:30~15:00 場所:戸坂公民館 主催:広島消費者協会戸坂地区
概要:新しい財産管理、家族信託の仕組みと上手な使い方を学びました。
参加者:16名

ごみ減らそうデー店頭キャンペーン(10月)
日時:2025年9月1日(月)11:00~ 場所:スパーク中山店
・ごみ減量・食品ロス削減啓発のぼり、パネルの掲示、啓発チラシの配布、買い物袋持参率の調査、ごみ減量・食品ロス削減に関するアンケートの実施、エコグッズの提供などを行いました。
消費者大学(第2回)「特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害防止策」
日時:2025年8月30日(土)13:30~15:30 場所:広島市消費生活センター研修室
講師:広島県警察本部特殊詐欺防止担当 課長補佐 土井 誠記 氏
参加者:23名

消費者大学(第1回)「消費者の役割(消費者問題、消費者行政など)」
日時:2025年8月23日(土)13:30~15:30 場所:広島市消費生活センター研修室
講師:広島市消費生活センター 消費者政策企画担当課長 関口岳史 消費生活相談員 麻田典子
参加者:27名
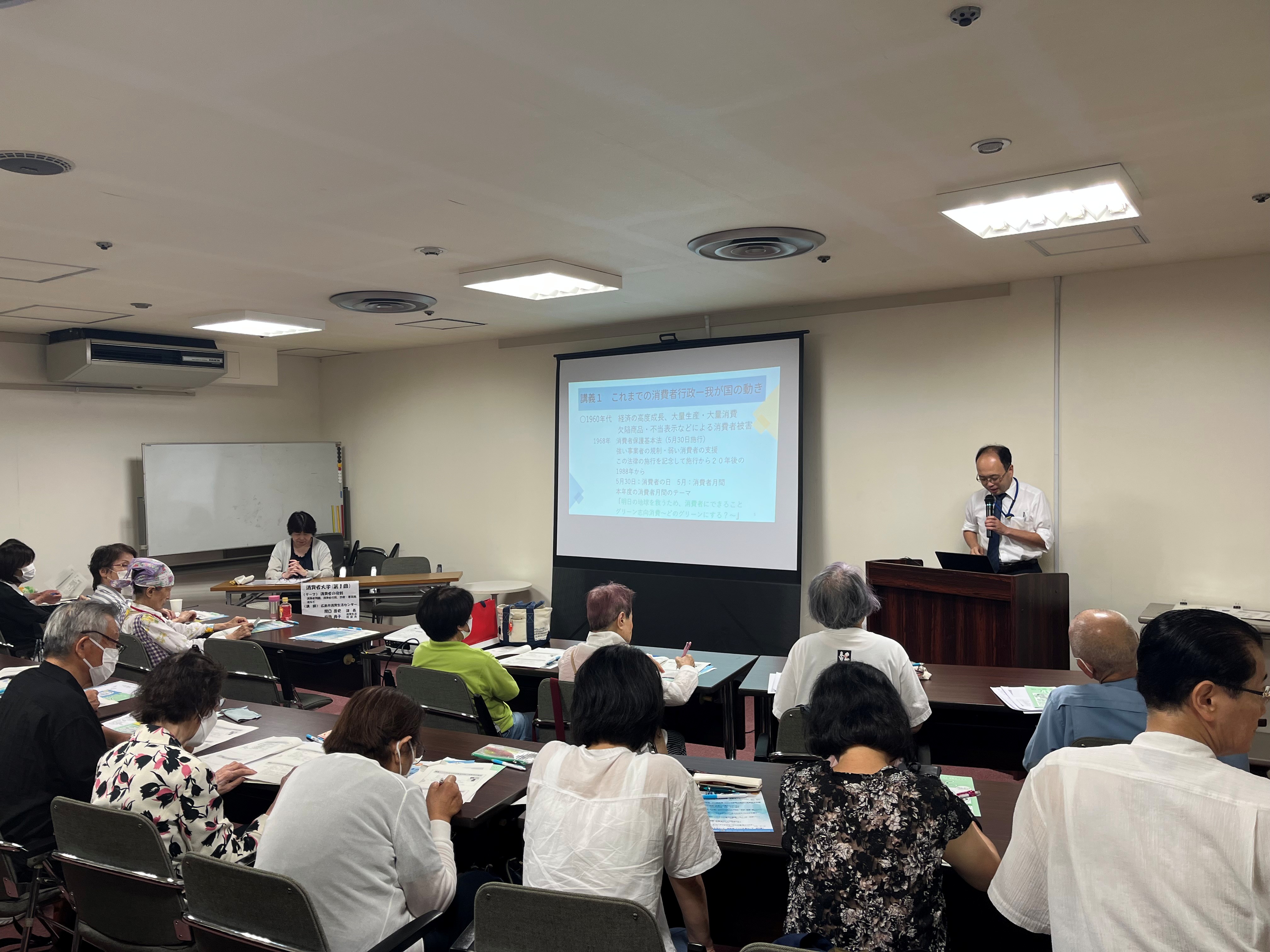
ごみ減らそうデー店頭キャンペーン(8月)
日時:2025年8月1日(金)11:00~ 場所:フレスタアルパーク店(西区井口明神一丁目)
・ごみ減量・食品ロス削減啓発のぼり、パネルの掲示、啓発チラシの配布、買い物袋持参率の調査、ごみ減量・食品ロス削減に関するアンケートの実施、エコグッズの提供、リサイクル工作教室などを行いました。

2025ひろしま温暖化ストップフェア(主催:広島市地球温暖化対策地域協議会)
日時:2025年7月23日(水)11:00~ 場所:紙屋町シャレオ中央広場

市民、事業者、行政が一体となって地球温暖化防止に向けた積極的な活動の推進を図るために開催された「2025 ひろしま温暖化ストップ!フェア」に参加しました。
消費者力向上キャンペーンinマツダスタジアム
日時:2025年7月17日(木)15:00~ 場所:マツダスタジアム
実施内容:うちわ1,900枚、啓発グッズ配布など啓発活動を行いました。

特殊詐欺・侵入犯防止セミナー「SNS詐欺、闇バイト強盗の実態と対策」
日時:2025年7月9日(水)14:00-16:00場所:広島市消費生活センター研修室(アクア広島センター街9階)内容:第一部:スマホを利用した特殊詐欺被害の実態、SNS型投資詐欺被害の防止 ソフトバンク株式会社
第二部:侵入強盗犯、特殊詐欺被害の防止 広島県警察本部
主催:広島消費者協会 参加者:30名

参加者全員が貸出スマートフォーンで広島県警察が作られた安全・安心アプリ「オトモポリス」を使って、防犯マップ、防犯ブザー、イーラーニングを実体験。オレオレ詐欺、預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺、架空料金請求詐欺、還付金詐欺、融資保証金詐欺、金融商品詐欺、ギャンブル詐欺、交際あっせん詐欺や侵入防止対策などについて学びました。
ごみ減らそうデー店頭キャンペーン(7月)
日時:2025年7月1日(火)11:00~ 場所:マルナカ白島店(中区西白島)
・ごみ減量・食品ロス削減啓発のぼり、パネルの掲示、啓発チラシの配布、買い物袋持参率の調査、ごみ減量・食品ロス削減に関するアンケートの実施、エコグッズの提供などを行いました。

中国チェッカ―接客対応審査会
日時:2025年6月27日(金)11:00~ 場所:広島市南区民文化センター
概要:スーパーマーケット等のレジ担当者の技術等を競う大会の審査員を務めました。
ひろしま気候変動適応セミナー「高齢者を守れ!熱中症の予防と知識」
日時:2025年6月11日(水)13:30~ 場所:広島YMCAコンベンションホール
主催:ひろしま気候変動適応センター
概要:「熱中症の現状と将来及びその対策について」国立環境研究所 岡 和孝 氏
「気候変動の時代、天気予報で生き延びる!」気象予報士 勝丸 恭子 氏
*熱中症予防、天気予報の上手な読み解き方などを学びました。
ごみ処理施設 安芸クリーンセンター 見学(安芸地区)
日時:2025年6月10日(火)13:30~ 場所:安芸クリーンセンター(安芸郡坂町)

リチウム電池によるごみ処理施設の事故被害が全国で発生しています。小さな電池ですがごみへの混入が大きな事故につながっています。特に携帯扇風機には気を付けましょう。また、捨てるときのことを考えて購入することの大切さをあらためて強く感じました。一市民、一消費者としてゴミとの関りを考える良い機会となりました。
ごみゼロ・クリーン・キャンペーン
日時:2005年6月8日(日)9:30- 場所:ひろしまスタジアムパーク
きれいなひろしま・まちづくり市民会議主催のクリーンキャンペーンで、ひろしまスタジアムパーク周辺の清掃活動に参加しました。
観世音陵苑~はなみずき~見学(安佐南地区)
日時:2025年6月7日(土)10:30- 場所:観世音陵苑~はなみずき~(西区観音四丁目)

近年、~終まい、という言葉を耳にする機会が増えてきた。各家庭での関心度も高くなりつつある現実の問題。「お墓」の存在は、とても重要なテーマだと認識し、屋内の納骨堂を拝見。設置スペースは上段が礼拝、下段が納骨と分離されている。複数故人様を同時に偲ぶことも可能でとても新しい感覚のお参り方法に少し驚きもあった。見送る人もいつかは静かに眠る。関係者が安心、感謝を胸に抱きながら手を合わせるひとときは、いつでも可能との話。遺影を見つめながら、元気だった頃に聞いていた声、言葉がふと思い出されるような空間。「供養」は前向きに自分らしく過ごせるための静かな繋がりタイムと言えるのではないだろうか。今後も多くの人にきっと必要とされ、穏やかな心持ちを与えてくれる一画になることと実感した。
令和6年度 事業報告書 発行
協会が令和6年度に実施した事業を取りまとめた「令和6年度事業報告書」を発行いたしました(令和7年5月)
ごみ減らそうデー店頭キャンペーン(6月)
日時:2025年6月2日(月)11:00~ 場所:マルショク旭店(南区旭一丁目)
・ごみ減量・食品ロス削減の取組の呼びかけ(啓発のぼりの掲示、啓発チラシの配布)、買い物袋持参率の調査、ごみ減量・食品ロス削減に関するアンケートの実施、エコグッズの提供などを行いました。

総会記念講演会の開催
日時 2025年5月26日(月) 14:00~15:30 広島商工会議所
テ―マ グリーン志向消費・エシカル消費~明日の地球を救うため消費者にできること~
講師 広島市消費生活センター消費者政策企画担当課長 弁護士 関口 岳史 氏
まだ多くの方が理解していない「グリーン志向消費、エシカル消費」について、わかりやすく解説していただきました。服で温度調節する。食べ残しをしない。過剰包装をしないなど、36項目のグリーン志向行動チェックリスト。強制労働や児童労働、貧困、環境に配慮した倫理的、道徳的な消費には企業だけではなく消費者として「使う責任」を果たす必要があるなど多くのこと学びました。
令和7年総会
日時 2025年5月26日(月) 13:00~13:40 広島商工会議所
議題 令和6年度事業報告、平和6年度決算報告、令和7年度事業計画
・議案書
栗原 理(理事・顧問) 消費者庁消費者支援功労者表彰の受彰
当協会の理事・顧問の栗原理に、消費者支援功労者表彰ベスト消費者サポーター章が授与されました。 消費者支援功労者表彰は、消費者利益の擁護・増進のために各方面で活躍されている者を毎年消費者庁が表彰する制度で、その中で、顕著な功績があったと認められる個人・団体へ授与される「ベスト消費者サポーター章」、を受彰したものです。 このことは、当協会の消費者支援の活動が評価されたものでもあり会員一同、受彰を喜ぶとともに、引き続き消費者が安全安心かつ円滑に生活を送れるよう、積極的に活動を続けてまいります。
写真は令和7年5月26日に、消費者庁政策立案総括審議官 藤本武士様ご臨席のもと行われた授与式の際に撮影されたものです。
広島ガスとの定例懇談会@エディオンピースウイング広島
2025年2月10日 ㈪14:00~16:30 エディオンピースウイング広島
広島ガスとの定例懇談会をエディオンピースウイング広島で開きました。なぜここでと思われるかもしれませんが、エディオンピースウイング広島は災害時緊急避難場所に指定されておりそこには、一般的な石油系非常用発電機に比べて即時性や平常時も使えるといった優位性を持ったガス発電装置が設置されており今回その見学もプログラムに組み込みまれていました。そのほか、カーボンニュートラルに向けた取組や電気事業への参入などについて学びました。
物流パートナーシップセミナー
2025年2月17日(月) 13:30~16:00 ホテルグランヴィア広島
「物流生産性を向上させるためのテクノロジーの活用」 ロジスティード㈱上席理事 重田雅史 氏
「地方創生の正しい処方箋~政治と経済の問題点を斬る~」 慶応義塾大学大学院教授 岸博幸 氏

広島県トラック協会主催のセミナーへ参加し、物流の効率化、経済振興に向けた日本の課題などについて学びました。
温暖化推進フォーラム2025
2025年2月7日(金)10:00~16:00 エールエールA館
講演「デコ活との連携によるライフスタイル変革の可能性」ワークショップ「、地域ならではの脱炭素アクションのアイデア」などが盛り込まれた温暖化を推進するフォーラムに参加しました。
勉強会 賢いスマートフォンの使い方
2025年1月27日(月)10:00~12:00 戸坂公民館
携帯電話を持っているが上手く使いこなせない、詐欺メールや海外からの電話トラブルなどに巻き込まれたくないなど、会員の皆さんの要望で開催しました。
公正取引委員会 消費者セミナー
競争と取引の基本ルール(景品表示法と最近の違反事例)
公正取引委員会事務総局中国支所 取引方法調査官 道下 正子 氏
2025年1月6日(月)13:30~15:15 広島市消費生活センター研修室

企業間の公正な競争があることにより、消費者は多くのものから安くて良い商品を選ぶことができ、企業のサービスも向上する。競争にはルールが守られることが大切で不当表示などで消費者がだまされないよう公正取引委員会は調査、取締りを行われている。このセミナーではステルスマーケティング告示など最新の違反例の具体的な紹介もありました。
勉強会「どうして減らないの?特殊詐欺」
2024年11月29日(金)10:00~11:30
講師:川村佐和子、田中美惠子
参加者の消費者トラブルを出し合い大なり小なりの身近なトラブルに気付きました。ネット通販の定期購入トラブルを政府広報動画で見たり実際の新聞折込広告で問題点や注意点を確認するなど今まさに多いトラブルについて説明を受けました。SNS型投資詐欺やロマンス詐欺などは被害額が大きくて身近にわながまかれています。自分に都合のよい情報を受け入れたがる心理が働くこと。何度も繰り返される情報を信じたくなる傾向にあることを知り引っ掛からないように気を引き締めようと思いました。「何よりも大事なことは地域の力で孤独にさせない!そして早めの相談を!」という講師の言葉が印象に残りました。
消費者のつどい2004「エシカル消費に向けて消費者ができることは何か」
2024年11月12日(火) サテライトキャンパスひろしま

消費者団体の活動報告や講演会を通じて消費者問題について考える「消費者のつどい2024」に参加しました。
産地交流視察事業(食協志和工場、サタケ㈱)
2024年11月11日(月)、会員27名が食協志和工場とサタケ(株)を訪問し、事業概要等の説明を受けながら工場内を見学し、食にかかわる取り組みの意見交換および研究を行った。
地元企業の食の安全性に対する取り組みを学び、その技術の高さ、真摯な姿勢に安心した。また、お米の企業2社を見学することで、それぞれの特色を知ることができた。
参加者の感想として、「食協の取り扱い数の多さに驚いた。」「わかりやすい説明だった。」「食べ比べはよかった。味が違っていた。」「米のネーミングなど、よく考えていると思った。」などがあった。

消費者大学の実施
2024年11月から7年1月土曜日13:30-15:30全8回 広島市消費生活センター研修室
広島消費者協会は広島市からの委託を受け消費者大学を実施しました。。

第1回 11/9(土)
オリエンテーション、消費者の役割(消費者問題、消費者行政など)
広島市消費生活センター 所長 山越重範 消費生活相談員 林敬二郎
第2回 11/16(土)
契約(特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺など)
広島県警察本部生活安全総務課 特殊詐欺防止担当 課長補佐 土井誠記
第3回 11/30(土)
インターネット(デジタルサービスの普及とリスク)
広島市電子メディア協議会 インストラクター 内海祐一郎
第4回 12/7(土)
生活設計(身元保証人、ファミリー信託、相続・遺言など)
なな行政書士法人 代表行政書士 岡村奈七江
第5回 12/14(土)
衣生活(素材、管理、サイズ、買い方など)
広島大学大学院 教授 村上かおり
第6回 12/21(土)
くらしの安全(製品安全4法、リコール、製品事故など)
中国経済産業局産業部消費経済課製品安全室 重田和哉 製品評価技術基盤機構 中国支所長 三谷誠二
第7回 1/11(土)
食生活(健康と栄養、高齢者の低栄養、フレイル予防など)
広島県栄養士会 管理栄養士 高畑江津子
第8回 1/ 18(土)
環境(地球温暖化問題:消費者としてできること)
広島消費者協会 理事 吉田悦子
食品ロス削減イベント「スマイルひろしま広場」
2024年10月27日(日)

まだ食べられるのに捨てられる「食品ロス」について学ぶイベント(広島市ごみ減量・リサイクル実行委員会主催)に参加協力しました。
勉強会「はぎれでつくるえんどう豆のストラップ」
2024年10月21日(月) 南観音公民館

捨てればごみ、生かせば資源の精神で端切れをつかいました。久し振りに会員様とお会いして和気あいあいとえんどう豆のストラップを作りました。お会いして色々な情報を交換することができました。皆さん公民館活動か熱心で日程調整が難しく参加者が少なく少し残念でした。
牛乳・乳製品料理コンクール
2024年10月19日(土) 進徳女子高等学校

広島県牛乳普及協会が主催される第45回牛乳・乳製品料理コンクール審査会に当協会の理事が審査員として参加しました。
モビリーデイズ勉強会
2024年10月7日(月) 広島市消費生活センター
講師:広島電鉄(株) 新乗車券システム推進部部長 福本将平 氏

9月から始まったモビリーデイズについて学ぶため、広島電鉄(株)から講師をお迎えしました。システム概要や具体的にどう使うのかを教えていただいた。参加者からは、制度自体への疑問や高齢者・障害者の立場にたった活発な意見や要望がありました。
島根原子力発電所見学
2024年10月4日(金)


中国電力の島根原子力発電所(以下、島根原発)を見学する機会を得た。本協会から15名の会員の参加があった。日常生活では縁のない電力供給の現場について学ぶと同時に、安全対策に関する具体的な取り組みを直接知ることが目的である。
まず、島根原子力館において原発の仕組みについて詳しい説明があった。これに関する詳細なメカニズムについては専門家に譲ることが健全であろう。ここでは少なくとも、リスクの伴う原発に対して最新の安全対策が取られていることを知り、その徹底ぶりを感じた。特に印象的だったのは、「多重防護」という考え方に基づく安全対策である。その一つに「物理的防護」がある。万が一の事故に備えて原子炉格納容器が二重構造になっており、放射性物質が外部に漏れないようになっている。また冷却システムも複数設けられており、一つのシステムが故障した場合でも他のシステムが冷却を続けられるように設計されている。
さらに、地震や津波といった想定外の自然災害への備えも徹底されていた。島根原発は地震に強い耐震設計が施されており、建物自体が非常に頑丈な構造になっている。津波に対する対策として、海側延長1.5kmにわたる、海抜15mの高さの防波壁や、浸水に備えた排水ポンプも備えられていた。あらためて発電所の安全性に対する信頼感が高まった。加えて、電源の喪失は大きなリスクとなるため、非常用電源が複数確保されていた。自然災害や予期せぬ事故の際も、冷却システムを維持するための電力が確保されている。
私たちが利用する電力の背景には多くの人々の努力と最新の技術に支えられていることがわかった。同時に原発に伴うリスクを正しく理解し、安全性を常に注意深く意識しながら、エネルギーミクスについて考える重要性を強く感じた。
なお、この見学会後、10月23日に島根原子力発電所2号機の特定重大事故等対処施設および所内常設直流電源設備(3系統目)の設置に係る原子炉設置変更許可申請について、原子力規制委員会から許可を受けたことが広報されている。
家電公取協との消費者懇談会
2024年9月27日(金) 合人ウェンディひとまちプラザ

店頭での販売員の商品説明も表示に当たることを学習し、消費者の話しをよく聞いてくれる販売店を選び、丁寧な説明を受けて、つまり表示を確認して、より生活が便利になる商品を選ぶことが大切であると再認識した。その他消費税表示や修理に関することなど幅広く学習した。
施設見学会
2024年9月13日(金)
㈱ベリーネぶどう(浜田市金城町)
2007年3月地元の建設会社と設立。現在は中電工グループ(株)ベリーネが運営する観光農園。豊かな自然囲まれた195アールのハウス農園で1月~5月いちご狩り、8月下旬~9月下旬頃までブドウの収穫体験ができる。ピオーネのハウスの中でピオーネに囲まれて、「30歳代を中心に運営をしているが自然との共生なので厳しい」などの話を聞いた。
西田和紙工房(浜田市三隅町)

重要無形文化財石州和紙・ユネスコ無形文化遺産石州和紙・伝統工芸品の石州和紙工房の西田和紙工房を見学。〈七代目西田誠吉さんの話〉地元の原材料にこだわり、材料から一寛して伝統の手漉き和紙の製造を行う。伝統技術の継承に重点を置きながら、未来に向かって和紙の可能性も求めている。以前は20数軒あった和紙工房も今は4軒になったが、石州和紙の技術の継承に力を注ぎたい。製造工程の見学➡楮(こうぞ)栽培(自宅の庭)→原木剝ぎ→黒皮乾燥→黒皮そぞり→煮熱→塵取り→紙漉き→千板貼り→天日乾燥→裁断→完成までの工程を見学。それぞれの工程を一人で黙々とこなしておられる姿に感銘を受けた。
消費者力向上キャンペーンinマツダスタジアム
2024年7月9日(火)

広島市消費生活センターと一緒にカープロゴうちわなどの啓発グッズの配付、消費生活クイズ・アンケートなど、消費者被害の防止、消費者力向上などの啓発活動を行いました。
中国チェッカーフェスティバル
2024年6月28日(金)広島市南区民文化センター
チェッカ―(レジ担当者)の速度、正確性、接客態度等を競う、㈱中国シジーシー主催のチェッカ―フェスティバルに当協会の理事が審査員として参加させていただきました。
施設見学
津島織物製造㈱(江田島市能美町)
2024年6月20日(木)

縦糸も横糸も全て紙で織る会社は国内に2社しかなく、そのうちの1社が津島織物製造㈱です。
静岡県に国内唯一の製紙糸工場があり、そこから大きな紙の米袋に入った紙糸が届きます。紙糸の湿度を保つのに米袋がよいのだそうです。製紙糸も紙織物も、市場は小さく、コツコツと頑張っている事業者さんがいるから残っている伝統織物です。
工場内には大きな機械類が何台も据えてあり、いずれも長年使用されたもので、調整や修理は社長自らが行い、部品を他者に求めるとコストがかかるので、ほぼ自前で調達しているとのこと。紙布の模様は代々受け継がれたパンチパターンで織っています。工場の隅々に歴史と苦労が偲ばれました。織物の95%は壁紙になっていて、大手住宅メーカーと提携しているそうです。紙製の壁紙は、高価ではあるが、吸湿性がいい、ジョイントが分かりにくい、ジョイントがはがれにくいなどのメリットがあります。
紙布で制作された照明の傘、バッグ、名刺入れなどを見学後、同じ敷地内の別棟の住居に入ると、玄関マット、壁掛け、間仕切り、襖、テーブル掛けなど紙織物製品が品よく飾られていて、会員は小品作りに制作意欲が湧き、紙布を購入して帰りました。
ごみ減らそうデー店頭キャンペーン


広島市ごみ減量・リサイクル実行委員会は、毎月1日を「ごみ減らそうデー」として、市内のスーパーマーケットの店頭で、パネル展示やチラシの配布、アンケート調査、買い物袋持参率調査などを行い、ごみの減量・リサイクルと食品ロス削減に向けた啓発活動を行っています。
当協会も次のとおり参加協力しました。
2024年6月3日(月)ピュアクックあさひが丘店
8月1日(木)イオン宇品店
9月2日(月)フレスタ温品店
10月1日(火)ハローズ草津新町店
11月1日(金)サンリブ五日市店
12月1日(月)フジグラン広島
2025年 2月3日(月)ユアーズ瀬野川店
補聴器勉強会
聞こえの田中 広島本通店
2024年5月27日(月)
最近「聞こえ」というものが個人差ではあるものの脳の健康にとても大切であるとのことを耳にする機会が増え、どのようにダメージを与えてしまうのか、実状を学びに出向いた。聞く力は脳からの指令で成り立っている。外的な刺激・悪影響で脳機能全体の低下が著しいとの話。認知症リスクも高くなりコミュンケーション不足からの人格変化へとつながる実例もある。定期的な自身の状態を知りケアすることが重要であるとの説明は納得できた。補聴器と集音器の違い、選択するポイント、料金面、元気耳で幸せな日常を末永くもちたいものである。
総会記念講演会 広島市のまちづくり~都心活性化の推進について~
広島市都市機能調整部長 梶谷直毅 氏
2024年5月27日(月) 15:15~15:45 広島商工会議所101号室

広島市の都心活性化に向けた将来像をわかりやすく解説し ていただきました。 講演では、平成29年3月に広島市が策定された「ひろしま都心活性化プラン」に掲げられている、 「都心にふさわしく広島の顔となる空間づくり」「国内外から人を惹きつける広島ならではの魅力づく り」「世界中から訪れる人にやさしい交通環境づくり」「安全・安心で快適な都心ライフを支える環境づ くり」の四つの基本方針と具体的な施策のていねいな解説とともに、広島駅周辺、紙屋町地区、広島城周辺など地域ごとに、今後の具体的な計画を、完成時期も交えながら動画も使いながら、わかりやすく 紹介していただきました。街づくりにあたっては、活性化のみならず、平和への思いを共有できる空間づくりや災害時の帰宅困難者への対応、低炭素など環境への配慮など、広島市が平和と文化の懸け橋となり、誰もが集えるにぎわいと交流の都市“ひろしま”を、将来像として描かれていることが、とてもよくわかりました。